あなたは、今日、何か心配なことを抱えていますか?
仕事のこと、お金のこと、人間関係のこと、健康のこと。
人生には、思い煩うことが、尽きません。
「明日の会議、うまくいくだろうか」
「今月の生活費、大丈夫だろうか」
「あの人は、自分のことをどう思っているだろうか」
そうした思い煩いは、夜も眠れなくさせ、食事も味わえなくさせ、仕事の効率も落とします。
つまり、思い煩いは、私たちの人生から、大切な時間と、大切なエネルギーを奪うのです。
多くの人は、その思い煩いと戦います。「考えないようにしよう」と。
でも、その努力は、ほぼ失敗に終わります。なぜなら、考えないようにしようとすることが、さらに、その思いを強くするからです。
では、思い煩いから、本当に自由になることは、できるのでしょうか?
古い書物の言葉
古代の知恵の書に、こんな言葉があります。
「常に喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。主は近い。何事も思い煩うな。いかなることについても、感謝をもって、祈りと願いをもって、あなたがたの求めをゆだねよ。そうすれば、人知を超えた神の平安が、あなたがたの心と思いとを、イエスの中において守るであろう。」(ピリピ4:4-7)
この言葉は、二千年前に書かれた、古代の手紙の一部です。当時の受取人たちは、迫害を受けていました。死の危険にさらされていたのです。
その中で、「何事も思い煩うな」と言うのです。
「何事も」——それは、小さなことだけではなく、死の危険さえ含まれるのです。
では、この言葉は、現実離れした、きれいごとなのでしょうか?
いいえ。この言葉は、非常に実践的な知恵なのです。
まず、「常に喜びなさい」という言葉に注目してください。
ここでの「喜び」とは、感情的な喜びではなく、「どんな状況にあっても、人生に意味がある」という認識です。
つまり、「この状況の中にも、意味を見出そう」ということなのです。
その認識があれば、思い煩いは、別の角度から見え始めます。
次に、「感謝をもって」という言葉です。
思い煩っている時、多くの人は、「足りないもの」「不安なもの」に焦点を当てています。
でも、「感謝をもって」というのは、「今、ある」ものに焦点を当てることです。
命がある。家がある。友人がいる。食べ物がある。
そうした「今、ある」ものに、意識を向けることで、思い煩いは、別のものに変わり始めるのです。
そして、最後に、「祈りと願いをもって、あなたがたの求めをゆだねよ」という言葉です。
ここでの「祈り」というのは、宗教的な儀式ではなく、「自分の思いや願いを、心の中で整理する」ということです。
つまり、思い煩うのではなく、「自分は、何を望んでいるのか」を明確にし、その望みを、どこかに「ゆだねる」ことです。
ゆだねるとは、「自分一人で、何もかもをコントロールしようとするのではなく、信頼できる何かに、その望みを預ける」ということです。
その行為が、心に、奇跡的な変化をもたらすのです。
なぜなら、「自分一人で背負っていた」思い煩いが、「誰かに預けた」という感覚に変わるからです。
その感覚が、「人知を超えた神の平安」です。
説明できない理由で、心が落ち着く。理屈ではなく、「大丈夫だ」という感覚が生まれるのです。
現代への適用
では、具体的に、この古代の知恵を、今の生活に、どのように活かすのでしょう?
まず、思い煩いに気づいたら、その思い煩いを、「紙に書く」ことをお勧めします。
「明日の会議が心配」「生活費が不足している」「あの人の評価が気になる」
そうした思い煩いを、書く行為によって、「心の中」から「紙の上」に出すのです。
すると、心が、少し軽くなります。
次に、その思い煩いについて、「感謝できることはないか」を、考えてみてください。
「この会議があるから、仕事をしている」「生活に向き合う機会がある」「その人の意見は、自分を成長させてくれる」
そうした「別の視点」から見ることで、思い煩いは、学びや成長の機会に変わります。
さらに、「この思い煩いについて、今、自分ができることは何か」を、考えてみてください。
会議の準備をする、生活費の見直しをする、その人と真摯に向き合う。
できることをしたら、あとは、「できることはしたから、あとは、どうなるかに任せよう」と、その望みを「ゆだねる」のです。
その「ゆだねる」という行為が、「思い煩い」から「心の平安」への転換点なのです。
私の経験から
私は、63歳でうつ病になり、失職した時、「思い煩い」の渦の中にいました。
給料がない。病気がある。将来がない。
その思い煩いは、昼夜を問わず、私の心を支配していました。
眠ることもできません。食事も味わえません。
その時、「何事も思い煩うな」という言葉に出会いました。
最初は、「そんなことできるはずがない」と思いました。
でも、その言葉に従ってみることにしたのです。
毎朝、目が覚めたら、「今日、できることは何か」を考える。医者に行く。仕事を探す。友人に相談する。
できることをしたら、あとは、「もう、これ以上は、自分ではどうにもできない。どうなるかは、任せよう」と、その望みをゆだねるのです。
その習慣を繰り返すことで、不思議なことに、思い煩いは、徐々に減り始めました。
今、81歳の私は、思い煩いが、ほぼ消えています。
なぜなら、「できることはする。できないことは、任せる」という習慣が、身についたからです。
その習慣が、「心の平安」をもたらしたのです。
心の平安への道
思い煩いは、誰にでもあります。それは、悪いことではなく、人間らしい証です。
でも、その思い煩いに、支配される必要はありません。
思い煩いに気づいたら、書く。感謝を見つける。できることをする。ゆだねる。
その四つのステップを、繰り返すことで、「心の平安」は、やってきます。
それは、問題が解決した時ではなく、「問題を抱えながらも、心が落ち着く」という状態です。
その状態が、本当の平安なのです。
今日、考えてみてください
あなたは、今、何に思い煩っていますか?そして、その思い煩いについて、「今、できることは何か」を、一度、考えてみてはいかがでしょう?


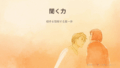
コメント